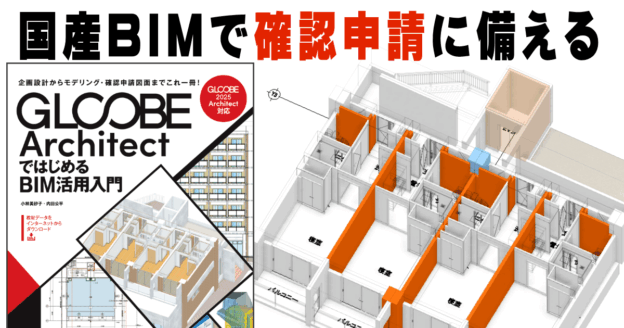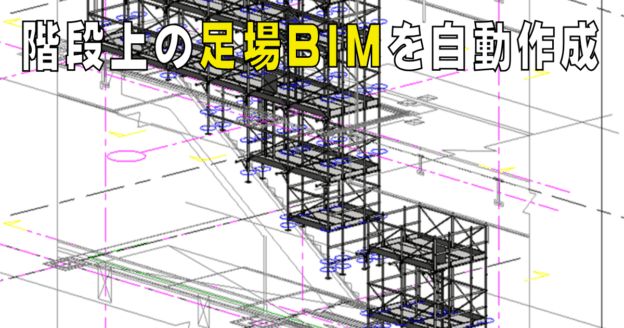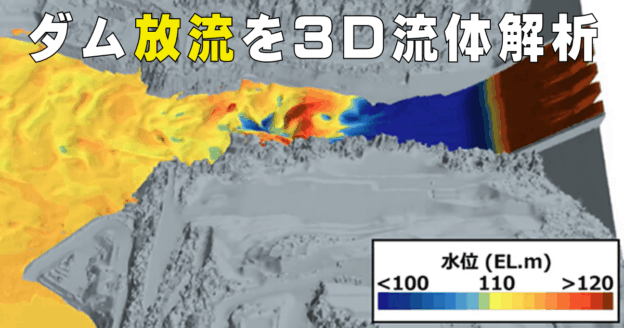管理人のイエイリです。
最近の建築設計では、カーボンニュートラルが重視され、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)などエネルギー性能の高い建築への関心が高まっています。
しかし建物のエネルギー計算を外注したり、専用ツールを導入したりするのは手間ひまやコストがかかるので、意匠や設備の設計を終えた後に省エネ計算を行うことが一般的でした。
こうした課題を解決しようとone building(本社:東京都目黒区)は、環境設計・ZEB検討ツール「BIM sustaina for Energy (Professional)」をリニューアルしました。
リニューアルのポイントはまず、これまでのRevitに加えて、
ナ、ナ、ナ、ナント、
Archicadでも設計中に
省エネ計算を何度も繰り返して行えるようになったことです。(one buildingのプレスリリースはこちら)
建物の省エネ計算は、建物が消費する一次エネルギーを基準値で割った「BEI(Building Energy Index)」の値を、国土交通省が提供する「WEBPRO」などのアプリで計算するのが基本です。
その計算を行うためには、入力データとして建物の概要や各部の断熱性能などをExcel形式でまとめた「様式A」と、空調・換気・給湯・照明などの建物内で使用する設備機器の仕様をまとめた「様式B」を準備する必要があります。
建物内にある膨大な数の部材や設備から、これらのデータを手作業で作成するのは大きな手間と労力がかかりますが、「BIM sustaina for Energy (Professional)」を使うと、BIMモデルの建築情報を使って数クリックで作成できるのです。
省エネ計算用のデータを手軽に作成できるため、意匠設計者は熱負荷や空調機器を変更しながら何度もBEIを計算し、少しずつ省エネ性能を高めていくことができます。
検討案はバージョン管理されるので、案ごとの比較検討もスムーズに行えます。
このほかBEIなどの計算結果に基づいて、ライフサイクル光熱費やCO2排出削減量など、
収益性や資産価値
に関連するレポートもワンクリックで作成し、複数の指標によって設計案の合意形成を後押しします。
このほか、契約の期間を従来の年間単位から1カ月単位に縮小し、プロジェクトごとに何人でも利用できるようになったので、必要なときに必要なメンバーが短期で利用しやすくなりました。対応のBIMソフトは、Revit2023/2024と、Archicad(バージョン27)です。
気になる利用料金ですが、小規模プラン(1000m2まで)が月額1万円(税別)、大規模プラン(5万m2まで)が同4万円(同)などとなっています。
このソフトの販売総代理店のTOPPANコスモ(本社:東京都千代田区)は、2025年4月22日(火)13:00~13:45にソフトのリニューアルや機能について紹介するウェビナーを開催します。ご興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。