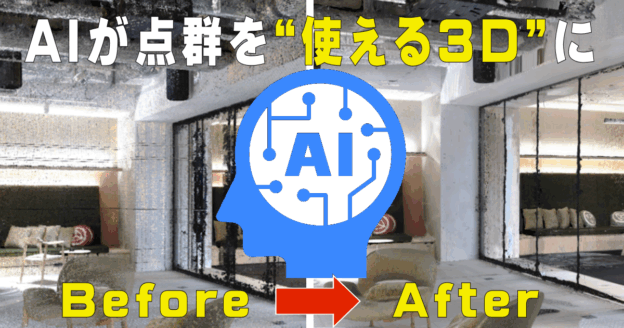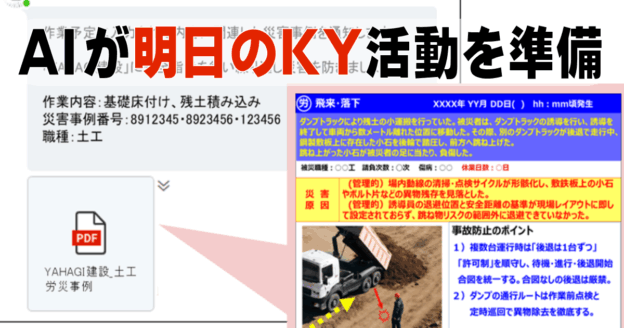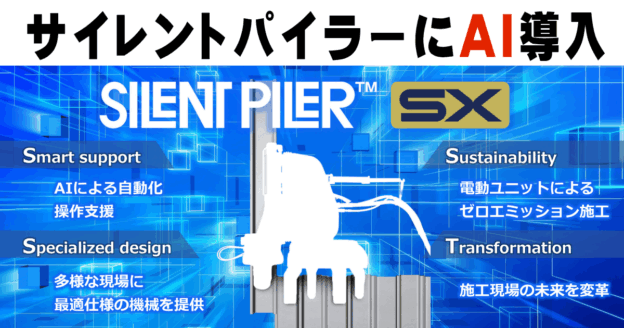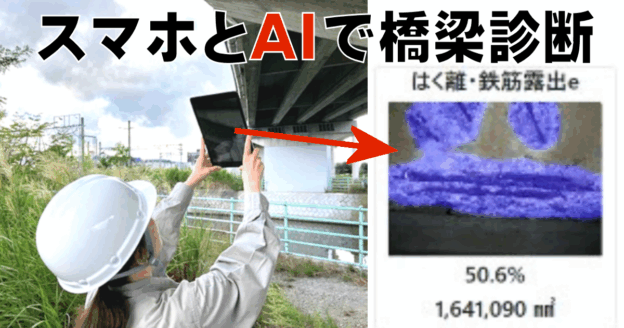管理人のイエイリです。
構造設計者は、建物に対する施主の要望と、構造の安全性や美観などを総合的に考慮し、構造部材を決めていきます。
その際に欠かせないのが「反復検討」です。鉄骨構造の場合、構造解析では部材の全体形状や部材断面を仮定してモデルを作り、構造計算を行って各部材の「持つ/持たない」を確認し、部材断面を変えてはまた計算する、といった作業を繰り返します。
この反復検討は、設計が進んだり、設計変更があったりするたびに行われるので、大変な手間ひまがかかっていました。
そこで大林組はギリア(本社:東京都台東区) の協力を得て、鉄骨の断面設計を自動で行う構造設計プログラムを開発しました。
多数の構造案を作ったり、反復検討を行ったりする作業を、
ナ、ナ、ナ、ナント、
AIで自動化
したのです。(大林組のプレスリリースはこちら)
基本設計段階では数多くの全体構造の候補から最適なものを選び出し、実施設計段階ではコストや施工性が最も有利となる部材断面の寸法や配置を絞り込んでいきます
AI(人工知能)プログラムは設計者が発案したA案、B案、C案といった基本的な構造形状から、数多くのバリエーションを作っていきます。そして設計者はこの中から最適なものを選びます。
従来は設計者が過去に経験した事例がベースだったので、検討できる案も限られていましたが、AIの活用で自分の枠を超えた幅広い検討が可能になります。
続く、実施設計では、AIプログラムはNG(持たない)部材や応力的に余裕のある部材の断面データを修正し、構造計算を行う、という繰り返し作業を自動的に行ってくれます。
そしてこれまで1週間を要していた断面設計が、わずか1日に短縮されるのです。
そのため構造設計者は、トライアンドエラーの単純作業から解放され、詳細構造の検討や要望への手厚い対応といった
付加価値の高い業務
に集中できるのです。
また、部材断面を再検討する過程や部材重量の変化を可視化する機能もあるので、構造設計者は最終結果だけでなく設計プロセスの過程も一目で把握できます。
この作業を通じて、構造設計者は視点を広げたり、建物特性への理解を深めたりといった「学び」も得られるのです。
このAIプログラムでは、構造部材を長さや地震力など荷重によってグルーピングを行う「クラスタリング」という教師データなしのAI手法や、構造設計者が蓄積してきたノウハウを数式化した「ルールベースAI」、そして制約条件のもとで最適な解を導き出す「数理最適化手法」(混合整数線形計画法)といった手法が使われています。
これまでは構造の最適化を行う際、プログラムを組んで部材の組み合わせを総当たり的に計算するといった方法が取られていましたが、AIによってより賢い繰り返し検討が実現できそうですね。
また毎回、プログラミングを行う必要がないのでAIによる構造設計の「ノーコード手法」とも言えそうです。
現在、このプログラムは鉄骨造建物を対象にしていますが、大林組は今後、鉄筋コンクリート造や混合構造への適応も進めていく予定です。また、設計プロセス全体を通じたAI活用も進め、構造設計者のニーズに沿った新機能の開発も行います。