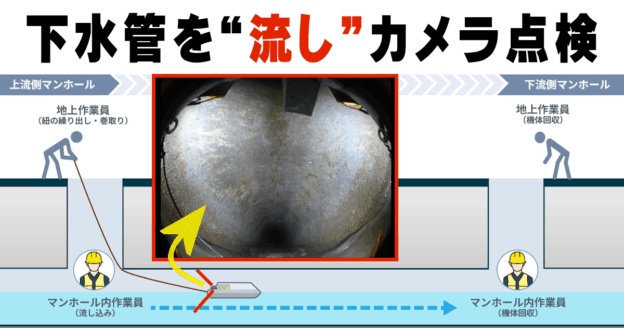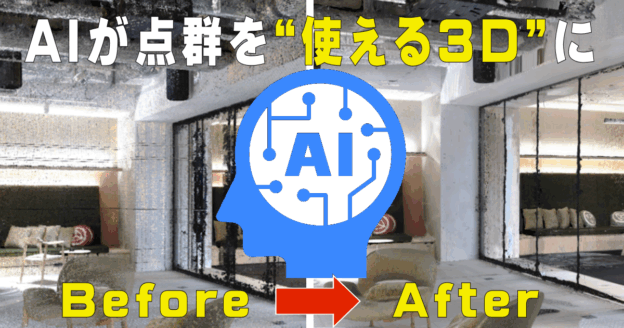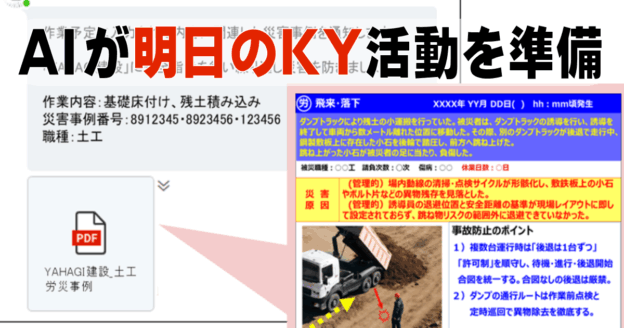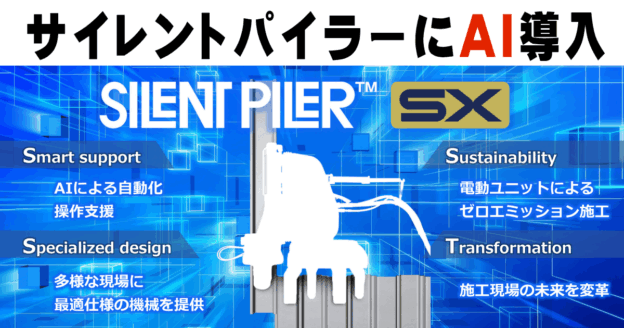管理人のイエイリです。
全国に約73万ある橋梁は老朽化が進みつつあり、国土交通省によると2023年度には建設後50年以上が経過するものが約59%になります。
一方、2024年には道路橋定期点検要領が改訂されて新様式となり、診断品質の均質化や診断根拠の詳細化、第三者へのリスクを踏まえた技術的見解の記述が求められるようになりました。
橋梁の維持管理現場では、ただでさえ熟練技術者が不足している中、診断の件数や求められる品質の水準が高まることで、担当者は頭が痛くなりそうですね。
そんな中、2025年4月~5月に長崎県内の13橋梁を対象にして、効率的に新様式の調書を作成する実証実験が行われました。
ナ、ナ、ナ、ナント、
生成AIに診断結果案
を作成させることにより、大幅な効率化を実現しようというものなのです。(NTTコムウェアのプレスリリースはこちら)
この実験は、NTTドコモが開発したAIエージェントを使用し、NTTコムウェア(本社:東京都港区)、長崎大学、溝田設計事務所(本社:福岡県久留米市)、長崎県建設技術研究センターが、連携して実施しました。
実験内容は、AIエージェントに橋梁の点検調書から損傷の種類や箇所、進行度などのデータを読み込ませ、道路橋定期点検要領などの基準類や診断のロジックを参照情報としながら、診断結果を新様式の調書にまとめさせるというものです。
その結果、1橋あたりの診断にかかる
作業時間は57%削減
できることが確認されました。
このほかノウハウの継承や技術者育成への活用、診断結果の均質化に加え、それによる補修判断の適正化や修繕コストの最適化につながることも確認されました。
人間が診断していると、どうしても担当者によって診断のレベルがぶれることがあり、その結果、損傷度の大きな橋の補修が後回しになって補修コストが増大してしまうこともありがちです。
生成AIの活用によって、いつでも均質な診断結果が得られると、こうしたぶれによる補修のムダも削減できそうですね。