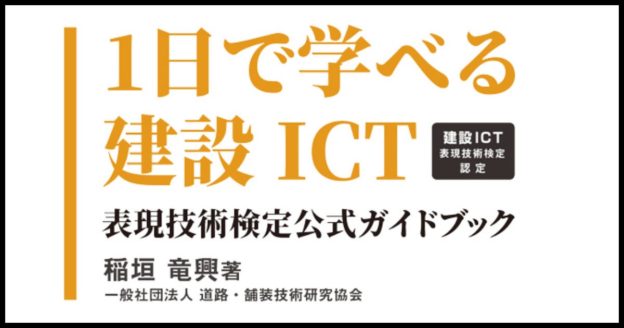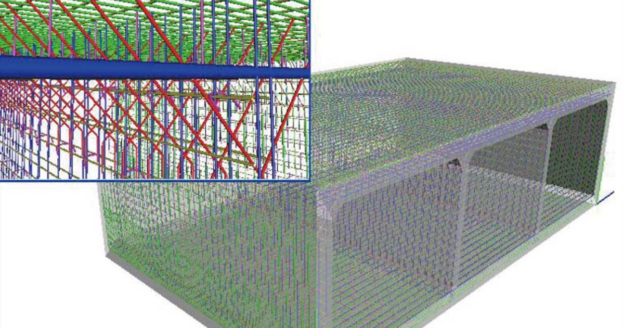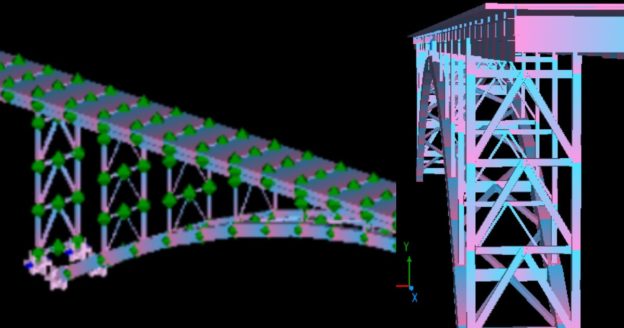フォーラムエイト(東京都港区)は、2025年4月から開催されている大阪・関西万博に催事パートナーとして参加した。一般来場者向けに「未来の月と宇宙のバーチャル体験」をテーマに、絶叫VRマシンや月面車、月面建機を操縦するVRシミュレーターを出展。わずか1カ月で5万人以上が体験した。未来の防災をテーマにトークセッションも開催し、予約で満員になる大盛況だった。その盛り上がりを現地取材で伝える。
 VRによる宇宙遊泳や月面運転の体験に長蛇の列が
VRによる宇宙遊泳や月面運転の体験に長蛇の列が
2025年5月1日から6月1日まで、大阪・関西万博会場内の「ロボット&モビリティーステーション」パビリオンで、フォーラムエイトは期間限定のバーチャル体験展示「未来の月と宇宙のバーチャル体験」を行った。
この展示は大阪大学の福田知弘教授の監修のもと、VR(バーチャルリアリティー)やデジタルツイン技術を駆使して月面環境を再現し、宇宙開発や月面生活を体験できるものだ。内装のデザインは、フォーラムエイトの武井千雅子取締役が担当した。
アメリカ館などでも、VRによる宇宙開発の展示はあるものの、来場者は「見る」だけだ。一方、フォーラムエイトの展示では、視覚だけではなく、VRと連動して座席が上下さかさまになる“絶叫マシン”や、座席が実車同様に揺れるシミュレーターによって、無重力や動きも体感できる点が魅力的だ。
そのため約1カ月の展示期間中、14万人を超えるブース来場者の中で約5万8千人が展示システムを体験し、非日常の空間を楽しみながら、宇宙遊泳や月面探検、月面での建設技術を実感することができた。
 上下に回転する“絶叫VRマシン”は90分待ち
上下に回転する“絶叫VRマシン”は90分待ち
展示は大きく3つの体験ゾーンに分かれていた。入口に近く、最も目立つのは「360°宇宙遊泳体験ゾーン」だ。
来場者はVRゴーグルを装着して座席につくと、目の前には宇宙ステーション内部の様子が立体的に映し出される。すると、座席がくるくると上下360度に回転する。無重力空間に放り出されるような浮遊感とスリルが特徴で、宇宙飛行士の訓練の一端を疑似体験できる。まさに絶叫マシン型のコンテンツだ。
そのため来場者の人気は高く、90分待ちの列ができることもあった。
 月面をジャンプしながらドライブする月面探検車
月面をジャンプしながらドライブする月面探検車
地球の約6分の1しかない月の重力を再現したVR空間で、月面探査車の運転を体験できるのが「月面走行シミュレーション体験ゾーン」だ。
スタート後、2つの関門を通過し、宇宙に輝く地球を目指してゴールするタイムを競う。フォーラムエイトが得意とする「ドライビングシミュレーター」を、月面の重力に合わせて設定したもので、ハンドル操作や月面の地形に合わせて座席が実際に傾き、振動することで臨場感を高めている。
重力が小さいため、地形に凹凸があるとすぐにジャンプする。その感覚がモニター画面とともに座席の揺れや振動からも体感できる。
混雑緩和のため、通常のモニター画面とハンドルだけで運転できるシミュレーターも5台用意れた。こちらは15分待ちくらいだが、何度も並んで楽しむ来場者が少なくなかった
 宇宙建設シミュレーション体験
宇宙建設シミュレーション体験
少しマニアックだったのが、月面基地建設をテーマにした「宇宙建設シミュレーション体験ゾーン」だ。実物の操作レバーをそのまま再現したコックピットから、月面のパワーショベルを遠隔操作し、制限時間内に「月の石」をどれだけ多く掘削できるかを競うゲームだ。
こちらも座席が傾いたり揺れたりする仕様になっており、仮想的な建設作業の臨場感を再現している。左右2本のレバーをそれぞれ前後・左右に動かすと、パワーショベルが旋回したり、アームやバケットが開閉したりする。
初めての人には難しいため、熱血指導スタッフが常駐し、来場者を応援しながらレバー操作のコツを教えていた。
この一連の展示は、いずれもフォーラムエイトが得意とする3Dデータ技術とシミュレーション環境構築力を生かし、未来の宇宙開発の可能性とVR技術の応用範囲を来場者に強く印象づけた。
 災害大国の日本から防災・減災を提言
災害大国の日本から防災・減災を提言
展示のほか、フォーラムエイトは5月20日、万博会場内のテーマウィークスタジオで、「あなたの安全・安心な未来に向けた、災害大国である日本だからこその世界への提言」と題したトークショーを開催した。
パネリストには地元の大阪大学大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻 教授の福田知弘氏、東北大学災害科学国際研究所教授・副学長の今村文彦氏、フォーラムエイト代表取締役社長の伊藤裕二氏が登壇し、テレビでもおなじみのタレント、パトリック・ハーラン(パックン)氏がモデレーターとしてトークを盛り上げた。災害大国としての日本からの提言に高い関心が寄せられ、定員約100人の会場は事前予約で満席となった。
 福田氏はMRによる災害リスクの見える化を提言
福田氏はMRによる災害リスクの見える化を提言
福田氏は「市民目線で分かりやすい、できるだけ正確な防災ツール」をテーマに、国内外の地震や台風、火災などの災害事例を紹介した。その中には大阪の街を襲った1995年の阪神淡路大震災や、2018年の大阪府北部地震や台風21号など、自分自身のリアルな災害経験も生々しく語った。
そのうえで提言したのは、一般市民が災害リスクに対する理解を深めるためのデジタル活用だった。例えば浸水シミュレーション結果を都市のデジタルツインと合成したり、MR(複合現実)システムによって自分の住んでいる街並みと洪水の水面を重ねて見たりすることで、平常時の街が洪水時にどうなるかを、わかりやすく見える化することの重要性だ。
このほか、洪水前後の街の画像をAI(人工知能)によって比較することで、洪水の浸水範囲を自動的に検出する技術なども紹介し、洪水などの被害状況を定量的かつ視覚的にわかりやすく把握できるようになった現在の技術についても紹介した。
 今村氏は複合災害への備えと避難を提言
今村氏は複合災害への備えと避難を提言
今村氏は「複合災害に備えよう、人流データ活用により避難行動の把握を」をテーマに、地震動や津波、土砂災害、原発事故などが連鎖する災害に対する備えの必要性を説いた。
2011年の東日本大震災から2024年の能登半島地震に至るまでの、地震や豪雨、土砂災害、火山噴火など数多くの災害が報道され、メディアから避難の呼びかけが行われているにもかかわらず、避難が遅れるケースが多くあることを指摘した。
その原因として、自分だけは大丈夫と思い込む「正常性バイアス」や、他の人を助けようとする「愛他行動」、自分はどうなってもいいという「自暴自棄」、そして周りのひとと同じ行動をとる「同調バイアス」があると指摘した。
一方、携帯電話の普及によって人々の現在位置を「人流データ」としてリアルタイムに把握できるようになったことで、避難行動の精密な分析ができるようになったことも報告した。能登半島地震で発生した津波では東日本大震災の教訓が生かされ、地震後20分くらいで安全な場所に移動できたことを報告した。
 伊藤氏はシミュレーションによる未来の予見を提言
伊藤氏はシミュレーションによる未来の予見を提言
伊藤氏は「科学的なシミュレーションによる災害体験と対策への気づきを深めよう」というテーマで、フォーラムエイトが取り組んできたシミュレーション技術による、未来の災害の気づきと対策の重要性について語った。
例えば1987年のフォーラムエイト創業以来、取り組んできた解析技術によって、実物の橋脚が地震などで破壊する過程を、精密な数値解析によって正確に予測し、2009年と2010年の解析コンテストで連続優勝したことを紹介した。
また、同社製品のユーザーである熊本県玉名市が、未来の津波被害や避難行動をVRシミュレーションによって予測し、市民に対する避難の重要性や災害リスクを深める教育に生かした例を紹介した。さらに同市ではこれらの結果をもとに避難ルートの設定や施設配置の検討など、防災計画にも活用していく方針であることを報告した。
イベントに先だって、英国グリニッジ大学 火災安全工学グループ教授のエドウィン・R・ガリア氏と、2024年に花蓮地震で被害に見舞われた台湾・花蓮県の徐榛蔚(ジョ・チェンウェイ)県知事がビデオメッセージで参加し、災害・避難シミュレーション技術による防災や、実際の震災での経験について語った。
 フォーラムエイトが一般来場者に与えたメッセージ
フォーラムエイトが一般来場者に与えたメッセージ
フォーラムエイトは本来、土木・建設・都市計画・防災など専門分野のプロフェッショナル向けにBtoBで事業を展開しているが、今回、大阪・関西万博という国際的な大イベントで宇宙や防災という誰もが関心を抱くテーマに同社の先端技術がどう活用されるかを、幅広い層にわかりやすく周知できた。
特に、子どもから大人までが一体となって参加できる体験型コンテンツと、専門性の高い国際対話を両立させた点は、フォーラムエイトが「VRで未来の建設や防災に貢献する企業」という印象を数多くの来場者に与えることができた。
今後もフォーラムエイトは、仮想と現実をつなぐ技術で社会課題の解決に貢献していく。
| 【問い合わせ】 | |
| 株式会社フォーラムエイト 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA 棟21F TEL:03-6894-1888 FAX:03-6894-3888 (各営業窓口はこちらをご覧ください) E-mail : forum8@forum8.co.jp |